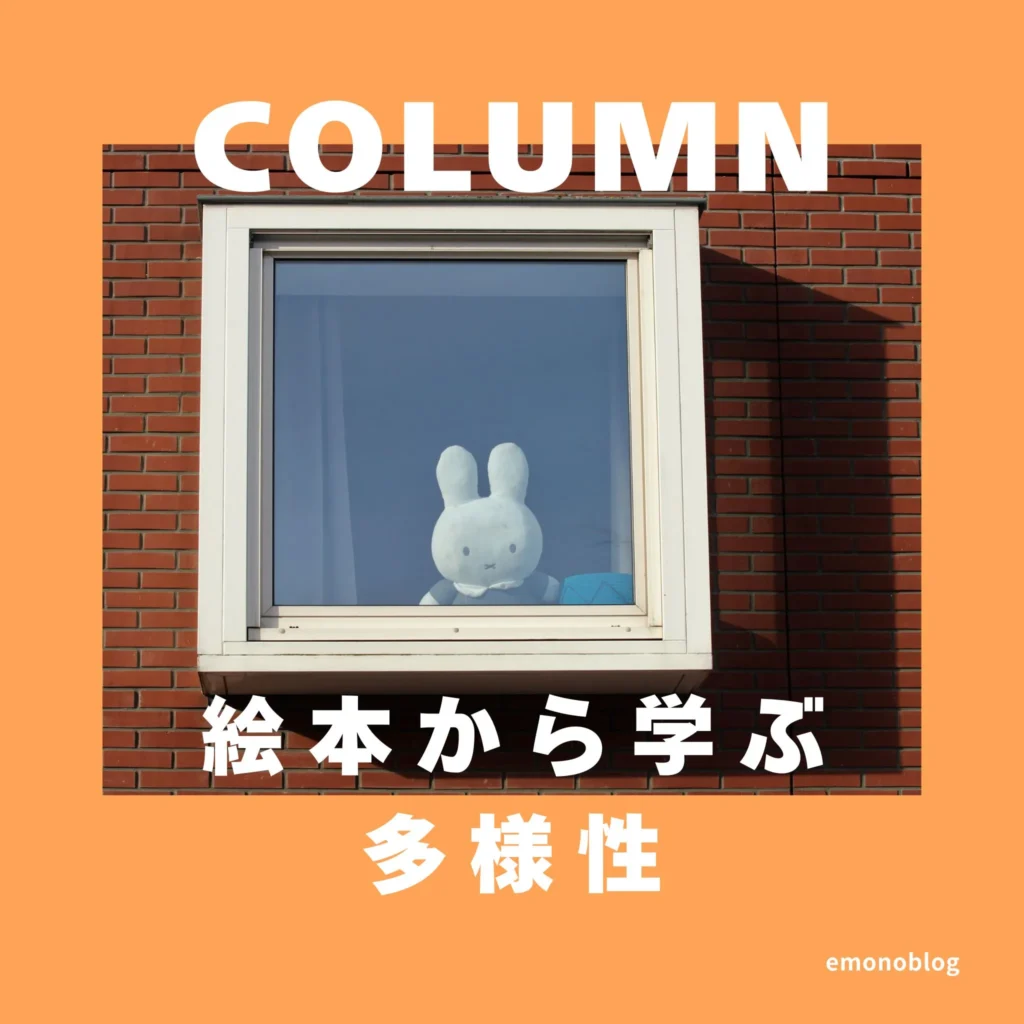
海外で暮らしていると、日々「多様性」に触れる機会がたくさんあります。
使う言葉も文化も違えば、肌の色や性のあり方も人それぞれ。そんな中で大切なのは、やっぱりお互いを尊重しながら生きていくことだなと感じています。
今回は、そんな「多様性」について、ミッフィーの絵本をきっかけに考えてみました。
筆者自身が感じたちょっとした違和感や気づきを、シェアできたらうれしいです。
うさこちゃんとにーなちゃん
ディック・ブルーナ著の「うさこちゃんとにいなちゃん」翻訳はまつおかきょうこさんです。
「ミッフィー」の愛称で親しまれてていますが、日本では「うさこちゃん」と呼ばれています。メラニーは「にーなちゃん」です!
【海外版】
あらすじ
遠い外国に住んでいる茶色いうさぎ、にーなちゃん。うさこちゃんの文通相手です。ある日、にーなから「うさこちゃんに会いに行くわ! 」という手紙が届きます。大喜びするうさこちゃん。そして待ちに待った日、にーなは飛行機に乗ってやってきます。すっかり意気投合したふたりは、かけっこやボール遊びをして仲良く遊びます。パジャマに着替えるとき、にーなのおなかを見たうさこちゃんは、その色がなんともうらやましく思えたのでした。
一見微笑ましい素敵なエピソードで、二人は一緒に遊び、笑い、仲良くなる中で、「見た目が違っても友だちになれる」というメッセージが自然に伝わってきます。
でもここでもうちょっと深掘りして考えてみます。
筆者が第一に思った事
筆者が最初に思ったのは、
「ミッフィー、それ、メラニーに言う最初の言葉なの?」ということでした。
メラニーはミッフィーの文通相手で、わざわざ遠い国から一人で飛行機に乗って会いに来てくれたのです。
それだけでもすごいことなのに、庭で一緒にボール遊びをしていたとき、ミッフィーが言ったのは
「メラニーちゃん あなたのいろ とてもきれいね すばらしい ちゃいろね」
いや、まずは「遠くから来てくれてありがとう」とかじゃない?と思ってしまいました。
もちろん、もしかすると空港で会ったときや家に着いたときに言っていたのかもしれません。でも、絵本の中ではそこに触れられていないんですよね。
そしてこの場面、本当に「平等」や「多様性」を描きたいのであれば、
メラニーのほうからも「あなたの白い肌も素敵ね」というような、お互いにリスペクトし合うセリフがあってもよかったのではないかと感じました。
さらに、夜寝る前のシーンでは、ミッフィーがこう言います。
「わたしのおなかも しろじゃなくて ちゃいろだったらよかったのに」
ここまで読んで、「さすがに肌のこと言いすぎじゃない?」と少し疑問に思ってしまったのも正直なところです。
多様性を伝える難しさ
もちろん、作者の「見た目が違っても仲良くなれるよ」というメッセージはしっかり伝わってきます。
絵本を通して子どもたちに「違いを受け入れることの大切さ」を伝えようとしている意図もよくわかります。
ただ、その“違い”を強調しすぎてしまうと、かえって違和感を覚えてしまうこともあるのが正直なところです。
「茶色い=違い=特別」という構図が、知らず知らずのうちに読み手の中に刷り込まれてしまうのでは?と思ってしまいました。
たとえミッフィーが善意で「あなたの茶色い肌、素敵ね」と言っていたとしても、その“見た目の違い”をあえて言葉にしてしまうことに、引っかかりを感じる人もいるかもしれません。
もし本当に多様性が“当たり前”に根付いた世界なら、「あなたの肌、とても素敵ね」と言うこと自体が、特別なことではなくなるはずです。
むしろ、「それ、わざわざ言う必要ある?」と感じる人がいても不思議ではないですよね。
最後に
メラニーの立場になって考えてみたとき、彼女がどんな気持ちで一人で遠くから来たのか…想像すると、すごく勇気のある子だなと感じました。
筆者自身も、過去にひとりで海外に行ったときの心細さを経験しているので、よりメラニーに共感できたのかもしれません。
だからこそ、絵本の中でも、メラニーのその「勇敢な行動」や「頑張り」にも少し触れてくれていたら、もっと心に残る作品になったのでは…と思う気持ちもあります。
今回は、ミッフィーの絵本を通して「多様性」について考えてみました。とても温かく素敵な絵本ではありますが、読み方によっては、作者の中にある無意識の“見た目の違い”への意識が、ふと見えてくることもあるのだと感じました。
読み手それぞれの立場や経験によって、絵本の感じ方も変わってくるもの。そんな視点を持って読むのも、ひとつの楽しみ方かもしれません。

